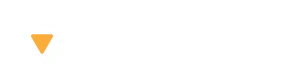September 24, 2025
台風襲来、避けられない天災。日本の対応戦略。
超大型台風「ラガサ」襲来:香港・台湾の被害と日本からの視点
今年第18号台風「ラガサ」は超強台風に分類され、その勢力は2018年に香港を直撃した「山竹」を上回るとされています。9月下旬に南シナ海へ進入後、華南や台湾に接近し、各地に暴風雨をもたらしました。
香港での被害
香港天文台は最高レベルの警告を発出し、市民に厳重な警戒を呼びかけました。市内では浸水や高潮が発生し、空港では国際・国内便が大規模に欠航、貨物便も大きな影響を受けました。公共交通は運休し、港湾作業も全面停止。結果として、香港発着の国際物流はほぼ麻痺状態に陥りました。
台湾での被害
台湾では特に東部と花蓮が深刻な被害を受けました。豪雨により山間部の天然ダムが決壊し、洪水が橋や道路を押し流しました。市街地も冠水し、多数の住民が孤立。死者・行方不明者が出ており、インフラの損壊によって物流や輸出入にも深刻な影響が及んでいます。
台風下における越境物流の実態
日本:極端気象に対する物流のレジリエンス
災害事例と影響:
日本の本州都市圏もまた、超大型台風によって深刻な被害を受けた経験があります。代表的な例として、2018年の台風「ジェービー(燕子)」が挙げられます。燕子は25年ぶりの強さで関西地方を直撃し、大阪関西国際空港は高潮による浸水で機能を停止、10日間にわたり閉鎖を余儀なくされました。暴風による高潮は滑走路を完全に水没させ、旅客ターミナルの電力設備も損傷しました。さらに不運なことに、5万トン級の大型タンカーが強風で錨地から流され、空港と本土をつなぐ唯一の連絡橋に衝突し、数千人の乗客と職員が空港島に孤立する事態となりました。関西空港は9月4日から全面的に離発着を停止し、すべての便が欠航、約5,000人の旅客が足止めされました。
空港閉鎖期間中、本来大阪から輸出されるはずの大量の貨物が他地域へ迂回、または倉庫で滞留することとなり、地域のサプライチェーンに大きな混乱をもたらしました。統計によると、関西空港はその会計年度において利益減少および復旧費用として約81億円(約7,500万米ドル)の損失を被りました。保険によっておよそ75%は補填されたものの、インフラが極端気象に対していかに脆弱であるかを浮き彫りにしました。さらに関西空港の停止は日本の他の港湾に大きな負荷を与え、多くの貨物機が中部国際空港や成田空港に臨時で着陸する事態となりました。
燕子台風だけでなく、大型台風は東京圏の物流にも深刻な影響を及ぼしています。2019年の台風「ハギビス(海貝思)」は首都圏の交通を壊滅的に打撃しました。当局は異例にも事前に首都圏鉄道の全面運休を発表し、成田・羽田の両空港もほぼ終日ゼロ便となり、日本の航空会社は合計で約2,000便を欠航しました。豪雨によって東京港の一部ターミナルが浸水し、クレーン設備も損壊しました。
東京や大阪には防潮堤や防風設備といった強固な耐災インフラが整備されているものの、近年相次ぐ台風被害によって物流は一時的に中断され、巨額の経済損失が発生しています。燕子台風の後、日本政府と業界は関西空港の停止による直接的な経済損失を数百億円以上と評価しました。
しかし、日本の物流システムは一定のレジリエンスを発揮しました。災害発生から数日以内に多くの国際輸送サービスが再開され、その後の増便や追加航路によって貨物の遅延が補われました。
予警と対応措置:
日本における台風予警は主に気象庁が発表する台風警報や暴風警報に基づいて行われます。香港のように明確な等級シグナルは存在しませんが、政府や企業は予報に応じて柔軟に対応します。一般的に、気象庁が大型台風の直撃を予測すると、国土交通省や地方自治体が防災会議を開催し、関係機関に防護措置を指示します。
航空会社や空港運営者は通常、1~2日前には運航調整を決定します。例えば2019年のハギビス台風では、航空会社は暴風到来の前日に東京の両空港における大部分の便の欠航を発表しました。JR東日本などの鉄道事業者も運休計画を早めに公表し、旅行者や荷主に準備時間を与えました。
運航停止の基準は事業者の判断による部分が大きく、例えば予測される最大瞬間風速が30メートル毎秒を超える場合、航空会社は自発的に便を欠航するのが一般的です。港湾については、各港湾局が気象庁の暴風警報を参考に閉港措置を発動します。港内で風力がビューフォートスケール10級(最大瞬間風速25~28メートル毎秒以上)に達すると予想される場合、港は船舶の入出港を禁止し、係留の強化や避難を指示します。同時に、コンテナヤードや倉庫では貨物の固定が強化されます。
また、日本の民間物流業者間には緊密な調整体制があります。台風接近時、多くの航空・海運会社は「前倒し出荷」や「配送延期」で協議します。越境宅配については、航空宅配業者や宅配会社が公式サイトで「特定期間、被災地宛の荷受け停止」を事前に告知し、緊急貨物には代替ルートの利用を推奨します。製造業者の中には、輸出製品を事前に空港や港へ搬入しておき、暴風通過後すぐに輸送できるよう備えるところもあります。
政府も「緊急物資輸送」制度を活用し、必要に応じて自衛隊や緊急便を調整して救援物資や重要貨物を優先的に輸送します。
総じて、日本の災害時の物流対応は「計画性」と「柔軟性」の両立を重視しています。早期警戒と逐次的な調整を求めつつ、官民協力によって台風通過後に迅速な物流回復を目指します。例えば、燕子台風後の関西空港では、わずか2日で1本の滑走路を仮復旧し部分運航を再開、一週間以内に主要貨物機能を復旧させました。これは政府による迅速な復旧資金の承認と、各航空会社の集中的な調整によるものです。
結論:もし台風が発生したなら…
もし台風が発生した場合、物流の遅延は避けられません。そのときに最も優先すべきは人命と安全です。いかに緊急の貨物であっても、一時的に輸送を停止し、従業員やドライバーの安全を第一に考える必要があります。
また、プラットフォームや購入者は自然災害による遅延を理解する傾向にあります。そのため、出品者は「配送が遅れる可能性がある」ことを事前に説明し、購入者の期待を調整することが重要です。
もしこれらを徹底するなら、台風通過後には物流の信頼性と効率を再び築くことができるでしょう。